2025年7月17日(木)第39回目の短編小説読書会を行いました。今回は5名での開催となりました。
今回のテーマは芥川龍之介『地獄変』でした。
芥川龍之介『地獄変』のあらすじ
平安時代、堀川の大殿に長年仕えてきた語り手が、大殿にまつわる数々の逸話の中でも、最も恐ろしい「地獄変の屏風絵」の由来を語る。
当時、良秀という名高い絵師がいた。傲慢な性格で人望はなかったが、十五になる娘には深い愛情を注いでいた。その娘は大殿の屋敷に小女房として仕えており、良秀は娘を返してほしいと何度も願い出たが、大殿に拒まれ続けた。
ある日、大殿は良秀に「地獄変」の屏風絵を描くよう命じた。写実を重んじる良秀は、弟子を鎖で縛ったりミミズクに襲わせたりして資料とし、絵を描いていたが、ある場面で筆が止まる。「燃え上がる車の中で苦しむ女の姿が描けない。私は見たものしか描けない」と訴えると、大殿は「望み通りにしてやる」と応じた。
数日後、火をかけられた車の中にいたのは、良秀の娘だった。娘を救おうとした良秀は止められ、やがて炎を前に立ち尽くし、壮絶な表情でその最期を見届けた。
ひと月後、良秀は絵を完成させ大殿に献上する。その出来栄えに周囲は言葉を失い、以後、誰も彼を悪く言わなくなった。だがその夜、良秀は自ら命を絶った。
初読の感想
まずは「審査員になったつもり」でこの作品を評価し、感想をシェアするところから始めました。
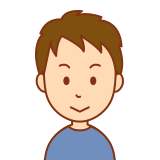
★★★★☆
長年大殿に仕えてきた人物が語り手となっている構成が興味深く、物語に深みが出ていると感じました。良秀の異常なまでの執念が強烈で、人物像が際立っていました。また、猿という動物の描写が、作品全体にどこか儚さや哀れさを添えていたのも印象的でした。
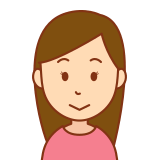
★★★☆☆
有名な作品なので、あらすじはすでに知っており、新鮮さはあまり感じませんでした。ただ、この語り手はいわゆる「信頼できない語り手」だと思います。全体を通して、大殿を擁護する立場から語っているように感じられ、その視点が物語に独特のバイアスを与えているように思いました。
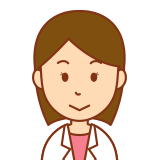
★★★☆☆
平安時代が舞台で、言葉遣いに難しさを感じました。芸術を追い求めるあまり、命すら顧みない姿勢にはゾッとさせられました。
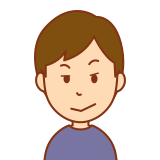
★★★★☆
考えさせられる作品でした。語り手の人間性は、疑って見る必要があると感じました。大殿と娘のあいだに何があったのかは最後まで気になりました。また、芸術にはある種の異常状態が必要なのかもしれないとも思いました。
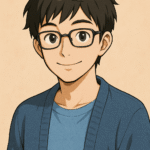
★★★★☆
さまざまな視点から読み応えのある作品だと感じ、個人的にはとても好きでした。語り手の信頼性や大殿と娘の関係性、猿という動物の象徴的な意味合いなど、考えどころが多く含まれていて興味深かったです。
今作の選定理由
今回の作品選定理由についてですが、前回の読書会で原田マハの『オフィーリア』を扱いました。その『オフィーリア』の創作にあたり、参考にされた作品が芥川龍之介の『地獄変』でした。そこで、比較の意味も込めて今回はこちらの作品を選びました。
考察①:信頼できない語り手(unreliable narrator)
最初に注目したいのは、『地獄変』の語り手である「長年仕えてきた家来」の語りのあり方です。一見すると彼は冷静で誠実な証言者のように映りますが、読み進めるうちに、その語りにはどこか不自然さや偏りが感じられる場面が出てきます。
彼の語りは、あくまで殿様に忠実な立場から語られており、出来事や人物に対する評価も一方的です。そのため、語られている内容すべてをそのまま信じることには慎重になる必要があります。このような語りの特徴から、彼は「信頼できない語り手(unreliable narrator)」として捉えることができる存在だと言えるでしょう。
語り手に対して疑問を持ちながら読むことで、『地獄変』という作品が単なる悲劇の記録ではなく、多層的な読みを許す構造を持っていることに気づかされます。
信頼できない語り手(unreliable narrator)とは
「信頼できない語り手」とは、物語を語る語り手の言葉や視点が、読者にとってそのまま信用できない、あるいは疑ってかかるべきものであると判断される語り手のことを指します。
語り手が「信頼できない」とされるのは、主に以下のようなタイプがあります。
◉「信頼できない語り手」の典型例
1. 虚偽タイプ
読者に故意に嘘をついている(自己をよく見せる、誰かを陥れるなど)。
2. 未熟・無知タイプ
子どもや知識の乏しい人物が語っており、読者のから見ると世界の見方が誤っている。
3. 精神的に不安定なタイプ
認知や記憶、現実認識にゆがみがある。
4. 偏見・自己中心タイプ
強い信念や思い込みに基づいて語るため、物事を客観的に見ることができない。
これらに共通するのは、「語り手自身が、自分の語りのゆがみに気づいていない」という点です。読者は、語られる出来事と語り手の視点とのズレに注目することで、その不信性を読み取ることになります。
◉なぜ「信頼できない語り手」を使うのか?
この手法にはいくつかの効果があります:
1. 読者との関係に緊張感を持たせる
「語り手=真実の語り部」という前提が崩れることで、読者は注意深く読まざるを得なくなる。
2. 物語に深みと謎を与える
読者は真実を一歩引いたところから探り、物語をより能動的に読み解くことになる。
3. 人間の主観や記憶の曖昧さを描く
人は必ずしも客観的ではいられないという現実を、文学的に表現する。
『地獄変』における、語り手の信頼できないところ
『地獄変』の語り手は、「殿様に仕える忠実な家来」という立場に強く縛られており、その語りもまた、あくまでその立場からの一方的な視点に偏っています。したがって、読者は語り手の言葉をそのまま鵜呑みにするのではなく、「この語りは何を隠し、何を歪めているのか?」という視点で読み取る必要があります。
それでは、具体的に見ていきましょう。
大殿を過剰に美化・擁護
あの方の御思召
は、決してそのやうに御自分ばかり、栄耀栄華をなさらうと申すのではございません。それよりはもつと下々の事まで御考へになる、云はば天下と共に楽しむとでも申しさうな、大腹中
の御器量がございました。
(芥川龍之介『地獄変』第一節)
大殿様が車を御焼きになつた事は、誰の口からともなく世上へ洩れましたが、それに就いては随分いろ/\な批判を致すものも居つたやうでございます。先
第一に何故
大殿様が良秀の娘を御焼き殺しなすつたか、――これは、かなはぬ恋の恨みからなすつたのだと云ふ噂が、一番多うございました。が、大殿様の思召しは、全く車を焼き人を殺してまでも、屏風の画を描かうとする絵師根性の曲
なのを懲らす御心算
だつたのに相違ございません。現に私は、大殿様が御口づからさう仰有
るのを伺つた事さへございます。(芥川龍之介『地獄変』第二十節)
物語の冒頭で大殿の偉大さを語る場面ですが、物語の展開やほかの描写と照らし合わせると、必ずしもそうとは思えない違和感が残ります。つまり、語り手は自分の立場や忠誠心から、大殿を過剰に正当化しようとしていると考えてもよい描写です。
物語の結末において、語り手は一見断定的な口調で語っていますが、「おつもり」「相違ございません」といった婉曲的な表現が多く、実際には主観や伝聞に基づいた曖昧な判断にすぎません。このように、語り手は確かな証拠を持っているように見せかけながらも、実際には噂話や主観的な推測に依拠しており、その語りには不安定さや不信感を抱かせる要素が色濃く含まれています。
娘を襲った真相を意図的に隠す
物語の中盤、語り手は良秀の娘が誰かに襲われたような描写を伝えますが、その相手が大殿なのか他者なのかは曖昧に描かれています。
すると娘は唇を噛みながら、黙つて首をふりました。その容子が如何にも亦、口惜しさうなのでございます。
そこで私は身をかゞめながら、娘の耳へ口をつけるやうにして、今度は「誰です」と小声で尋ねました。が、娘はやはり首を振つたばかりで、何とも返事を致しません。いや、それと同時に長い睫毛の先へ、涙を一ぱいためながら、前よりも緊く唇を噛みしめてゐるのでございます。
性得愚な私には、分りすぎてゐる程分つてゐる事の外は、生憎何一つ呑みこめません。でございますから、私は言のかけやうも知らないで、暫くは唯、娘の胸の動悸に耳を澄ませるやうな心もちで、ぢつとそこに立ちすくんで居りました。尤もこれは一つには、何故かこの上問ひ訊すのが悪いやうな、気咎めが致したからでもございます。――
それがどの位続いたか、わかりません。が、やがて明け放した遣り戸を閉しながら少しは上気の褪めたらしい娘の方を見返つて、「もう曹司へ御帰りなさい」と出来る丈やさしく申しました。さうして私も自分ながら、何か見てはならないものを見たやうな、不安な心もちに脅されて、誰にともなく恥しい思ひをしながら、そつと元来た方へ歩き出しました。
(芥川龍之介『地獄変』第十三節 ※太線は本ブログ執筆者による)
「生得愚かな私には、〜〜」という自己卑下的な言い回しは、何か重大なことを察しつつも、真実を隠したり伝えることを避けたりしていることを示唆しています。
「それがどの位続いたか、わかりません。」という表現は、語り手が時間の経過について曖昧にしていることで、出来事の正確な状況把握や記憶に不確かさがあることを示しています。この曖昧さは、語り手が見たくない、あるいは認めたくない出来事から距離を置こうとする心理的な回避とも考えられます。
考察②:人間性の喪失によって達する芸術至上主義
芥川龍之介『地獄変』において描かれるのは、芸術という崇高な目的のために人間性を犠牲にする姿です。しかし最初からそうだったわけではありません。この節では、絵師・良秀がいかにして人間性を捨てて究極の美を体現したのか、大殿の人間性と対比的に読み解いていこうと思います。
地獄「っぽい」ものを模索する良秀
絵師・良秀が屏風の注文を受けた際、写実をモットーとする彼は、できる限り地獄の様子を忠実に再現しようと努めておりました。また、偶然そのような場面に出くわした際には、スケッチを行うこともありました。
とはいえ、実際に人を殺すところまでは至っておらず、寸前のところで止めております。つまり、この時点では良秀にはまだ人間性が残っていたと考えられます。弟子を鎖で縛り上げ、毒蛇に噛ませようとする場面においても、直前で蛇を押さえております。見たものしか描けないとしながらも、本当に人が死ぬところまでは求めていなかったのです。
が、もし何事も起らなかつたと致しましたら、この苦しみは恐らくまだその上にも、つゞけられた事でございませう。幸(と申しますより、或は不幸にと申した方がよろしいかも知れません。)暫く致しますと、部屋の隅にある壺の蔭から、まるで黒い油のやうなものが、一すぢ細くうねりながら、流れ出して参りました。それが始の中は余程粘り気のあるものゝやうに、ゆつくり動いて居りましたが、だん/\滑らかに、辷り始めて、やがてちら/\光りながら、鼻の先まで流れ着いたのを眺めますと、弟子は思はず、息を引いて、
「蛇が――蛇が。」と喚きました。その時は全く体中の血が一時に凍るかと思つたと申しますが、それも無理はございません。蛇は実際もう少しで、鎖の食ひこんでゐる、頸の肉へその冷い舌の先を触れようとしてゐたのでございます。この思ひもよらない出来事には、いくら横道な良秀でも、ぎよつと致したのでございませう。慌てて画筆を投げ棄てながら、咄嗟に身をかがめたと思ふと、素早く蛇の尾をつかまへて、ぶらりと逆に吊り下げました。蛇は吊り下げられながらも、頭を上げて、きり/\と自分の体へ巻つきましたが、どうしてもあの男の手の所まではとどきません。
「おのれ故に、あつたら一筆を仕損じたぞ。」
良秀は忌々しさうにかう呟くと、蛇はその儘部屋の隅の壺の中へ抛りこんで、それからさも不承無承に、弟子の体へかゝつてゐる鎖を解いてくれました。それも唯解いてくれたと云ふ丈で、肝腎の弟子の方へは、優しい言葉一つかけてはやりません。大方弟子が蛇に噛まれるよりも、写真の一筆を誤つたのが、業腹だつたのでございませう。――後で聞きますと、この蛇もやはり姿を写す為にわざ/\あの男が飼つてゐたのださうでございます。
(芥川龍之介『地獄変』第九節)
意地悪を仕掛ける大殿、受けて立つ良秀
物語が動き出すのは十五節、あともう少しで屏風が完成しそうな良秀が大殿と面会する場面です。
少し長いですが、この部分を引用します。
「私は屏風の唯中に、檳榔毛の車が一輛空から落ちて来る所を描かうと思つて居りまする。」良秀はかう云つて、始めて鋭く大殿様の御顔を眺めました。あの男は画の事と云ふと、気違ひ同様になるとは聞いて居りましたが、その時の眼のくばりには確にさやうな恐ろしさがあつたやうでございます。
「その車の中には、一人のあでやかな上臈が、猛火の中に黒髪を乱しながら、悶え苦しんでゐるのでございまする。顔は煙に烟びながら、眉を顰めて、空ざまに車蓋を仰いで居りませう。手は下簾を引きちぎつて、降りかゝる火の粉の雨を防がうとしてゐるかも知れませぬ。さうしてそのまはりには、怪しげな鷙鳥が十羽となく、二十羽となく、嘴を鳴らして紛々と飛び繞つてゐるのでございまする。――あゝ、それが、その牛車の中の上臈が、どうしても私には描けませぬ。」
「さうして――どうぢや。」
大殿様はどう云ふ訳か、妙に悦ばしさうな御気色で、かう良秀を御促しになりました。が、良秀は例の赤い唇を熱でも出た時のやうに震はせながら、夢を見てゐるのかと思ふ調子で、
「それが私には描けませぬ。」と、もう一度繰返しましたが、突然噛みつくやうな勢ひになつて、
「どうか檳榔毛の車を一輛、私の見てゐる前で、火をかけて頂きたうございまする。さうしてもし出来まするならば――」
大殿様は御顔を暗くなすつたと思ふと、突然けたたましく御笑ひになりました。さうしてその御笑ひ声に息をつまらせながら、仰有いますには、
「おゝ、万事その方が申す通りに致して遣はさう。出来る出来ぬの詮議は無益の沙汰ぢや。」
私はその御言を伺ひますと、虫の知らせか、何となく凄じい気が致しました。実際又大殿様の御容子も、御口の端には白く泡がたまつて居りますし、御眉のあたりにはびく/\と電が走つて居りますし、まるで良秀のもの狂ひに御染みなすつたのかと思ふ程、唯ならなかつたのでございます。それがちよいと言を御切りになると、すぐ又何かが爆ぜたやうな勢ひで、止め度なく喉を鳴らして御笑ひになりながら、
「檳榔毛の車にも火をかけよう。又その中にはあでやかな女を一人、上臈の装をさせて乗せて遣はさう。炎と黒煙とに攻められて、車の中の女が、悶え死をする――それを描かうと思ひついたのは、流石に天下第一の絵師ぢや。褒めてとらす。おゝ、褒めてとらすぞ。」
大殿様の御言葉を聞きますと、良秀は急に色を失つて喘ぐやうに唯、唇ばかり動して居りましたが、やがて体中の筋が緩んだやうに、べたりと畳へ両手をつくと、「難有い仕合でございまする。」と、聞えるか聞えないかわからない程低い声で、丁寧に御礼を申し上げました。これは大方自分の考へてゐた目ろみの恐ろしさが、大殿様の御言葉につれてあり/\と目の前へ浮んで来たからでございませうか。私は一生の中に唯一度、この時だけは良秀が、気の毒な人間に思はれました。(芥川龍之介『地獄変』第十五節 ※太線は本ブログ執筆者による)
この部分を読むと、良秀は檳榔毛の車を一輛火にかけてほしいとは言っているものの、中に人間を乗せてほしいとは明確には言っておりません。しかし、大殿は良秀の言葉の空白を補完する形で、燃えている車の中に上臈を乗せることを決めたという流れになっています。良秀は口では「難有い仕合でございまする」と述べていますが、その様子は急に顔色を失い、喘ぐようにただ唇を動かしているだけで、やがて体中の筋肉が緩んだかのように、べたりと畳に両手をつくといった状態でした。したがって、本気で望んでいたのかは疑わしく思われます。この場面は、良秀の中で人間性と芸術家としての好奇心が揺れ動いていることを示しているのではないでしょうか。
燃える車を見た良秀と大殿の対比
火に包まれた車と娘の断末魔を前にしたとき、良秀と大殿の姿勢は対照的です。
良秀は、娘の死という極限状況にありながらも、まるで神がかったような威厳と集中を見せています。語り手はその姿を「夢に見る獅子王の怒り」「円光の如く懸つてゐる威厳」とまで形容し、まるで仏の啓示に触れたかのような荘厳な感覚を語っています。鳥ですらその威厳を察知して近づけないという描写は、良秀がすでに人間性を超越し、芸術そのものに同化した存在になったことを象徴しています。
一方で、大殿は「口元に泡を御ためになりながら」「獣のやうに喘あへぎつゞけて」おり、肉体的にも精神的にも動揺しています。表面上は権力者として振る舞っていた大殿が、芸術の場面ではむしろ人間的な弱さや不安定さを露呈しているのです。これは、芸術の力が権力をも凌駕する場面でもあり、同時に良秀と大殿の立場の逆転を暗示していると読めます。
その火の柱を前にして、凝り固まつたやうに立つてゐる良秀は、――何と云ふ不思議な事でございませう。あのさつきまで地獄の責苦に悩んでゐたやうな良秀は、今は云ひやうのない輝きを、さながら恍惚とした法悦の輝きを、皺だらけな満面に浮べながら、大殿様の御前も忘れたのか、両腕をしつかり胸に組んで、佇んでゐるではございませんか。それがどうもあの男の眼の中には、娘の悶え死ぬ有様が映つてゐないやうなのでございます。唯美しい火焔の色と、その中に苦しむ女人の姿とが、限りなく心を悦ばせる――さう云ふ景色に見えました。
しかも不思議なのは、何もあの男が一人娘の断末魔を嬉しさうに眺めてゐた、そればかりではございません。その時の良秀には、何故か人間とは思はれない、夢に見る獅子王の怒りに似た、怪しげな厳さがございました。でございますから不意の火の手に驚いて、啼き騒ぎながら飛びまはる数の知れない夜鳥でさへ、気のせゐか良秀の揉烏帽子のまはりへは、近づかなかつたやうでございます。恐らくは無心の鳥の眼にも、あの男の頭の上に、円光の如く懸つてゐる、不可思議な威厳が見えたのでございませう。
鳥でさへさうでございます。まして私たちは仕丁までも、皆息をひそめながら、身の内も震へるばかり、異様な随喜の心に充ち満ちて、まるで開眼の仏でも見るやうに、眼も離さず、良秀を見つめました。空一面に鳴り渡る車の火と、それに魂を奪はれて、立ちすくんでゐる良秀と――何と云ふ荘厳、何と云ふ歓喜でございませう。が、その中でたつた、御縁の上の大殿様だけは、まるで別人かと思はれる程、御顔の色も青ざめて、口元に泡を御ためになりながら、紫の指貫の膝を両手にしつかり御つかみになつて、丁度喉の渇いた獣のやうに喘ぎつゞけていらつしやいました。……
(芥川龍之介『地獄変』第十九節 ※太線は本ブログ執筆者による)
このように、良秀は人間性を喪失しながらも芸術の頂点に達し、大殿は権力者でありながらその芸術の前で無力さをさらす存在として描かれています。まさにこの対比は、『地獄変』が持つ芸術至上主義と人間性の喪失という主題を象徴的に浮かび上がらせる場面だと言えるでしょう。
物語を通して芥川は、芸術が人間性を超える価値を持ちうるという思想に、どこか肯定的な視線を注いでいるように個人的には感じられたのですが、皆さんはいかが思われますでしょうか。
考察③:「猿」が物語にもたらす効果
芥川龍之介の『地獄変』に登場する「猿」は、単なる動物ではなく、物語の構造と主題を支える象徴的な存在として、多層的な意味を担っています。
まず、猿は絵仏師・良秀の鏡像的存在として描かれています。良秀は「猿のような顔立ち」と形容され、外見的にも猿と重ねられています。そして猿が唯一心を許す相手が良秀の娘である点からも、猿は良秀の内面や欲望を映し出す象徴と解釈できます。すなわち、娘への深い執着や、孤独、そして人間的な弱さを体現しているのです。実際、読書会の参加者から「猿は良秀の善性を象徴しているのではないか」との指摘がありましたが、とても面白い意見だと思います。
まとめ
今回は芥川龍之介『地獄変』を、参加者の皆さんと意見を交わしながら読み進めました。多角的に読み解ける作品で、感想をシェアする中で新たな視点に気づかされることも多く、とても刺激的な時間となりました。元になった『宇治拾遺物語』にも触れたかったのですが、時間の都合で今回は見送ることに。
次回の読書会も、新しい物語と出会い、語り合えるひとときになることを楽しみにしています。初めての方も、どうぞお気軽にご参加ください!
次回は、江國香織の『すいかの匂い』を取り上げます。8月に読むにふさわしい短編小説です。
日程は決まり次第、こちらのブログにてお知らせします。
次回のご参加も心よりお待ちしております。



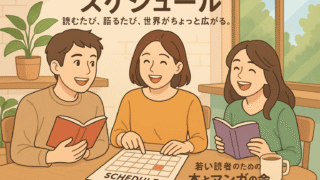

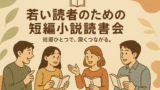

コメント