2026年2月12日(月)第43回目の短編小説読書会を行いました。
今回のテーマは魯迅『故郷』でした。
魯迅『故郷』のあらすじ
主人公の「私」は、家を処分するため、数年ぶりに中国の故郷の町へ帰ってきます。幼い頃に親しく遊んだ友人・閏土(ルントゥ)との再会を楽しみにしていました。
子どもの頃の閏土は、自然の中を自由に駆け回り、知恵があり、活き活きとした存在でした。「私」にとって彼は、憧れのような友だちだったのです。
しかし、大人になって再会した閏土は、貧しさと重い生活の責任に縛られ、かつての明るさを失っていました。身分差や社会的な立場の違いを強く意識し、「私」に対してもよそよそしく、距離を取ります。「私」は、昔の友情がそのまま続くと思っていた自分の甘さと、人を変えてしまう社会の現実を痛感します。
物語の終盤、「私」は次の世代である甥の宏児(ホンアル)と、閏土の息子水生(シュイション)の姿を見て、「子どもたちの未来には、今とは違う希望があってほしい」と願います。
感想のシェア
参加者の自己紹介をし、まずは「審査員になったつもり」でこの作品を評価し、感想をシェアするところから始めました。
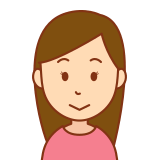
(事務)
★★★★☆
昔学校で教わった時はラストの段落がとても好きで気に入っていました。今回は新しい訳で読み直しましたが、受ける印象がかなり違いました。
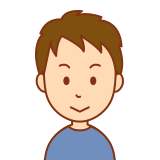
(クリエイター)
★☆☆☆☆
今回は感想が何も出てこないくらい印象がありませんでいた。確かに共感できるものはあったが、物語というよりは人の日記を覗き見している感じで面白さがないと感じました。
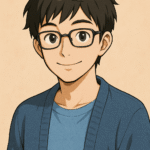
★★★★☆
もともと魯迅は社会を変えるために文学を志した経緯があり、非常に思想の強い作品が多く、個人的にはその作品が好きでした。過去を懐かしむと同時に社会への鋭い批判と、かすかな希望が感じられます。
今作の選定理由
今回、読書会の課題作に故郷を選んだのは、中学生の頃に一度は読んだことがある作品を、大人になった今の自分の感覚でもう一度読み直してみたかったからです。
当時は「昔の中国の話」という印象が強かったこの作品も、年齢や経験を重ねた今読むと、人との距離感、格差、希望や諦めといったテーマがより身近に感じられるのではないかと思いました。
「昔読んだはずの物語が、今読むとどう変わって見えるのか」。その違いを参加者のみなさんと一緒に味わい、語り合えたらと思っています。
魯迅の生涯と作風について
中学生の頃、魯迅の『故郷』を読んで、難しく感じた人は少なくないはずです。それもそのはずで、時代、言葉、文化が何もかも違うお話を、現代の日本人が読むわけですから、作品の面白さに辿り着くまでのハードルがかなり高くなっています。
ここでは作者の魯迅とその時代について、簡単におさらいしておきましょう。
1. 魯迅の生涯(1881–1936)
魯迅は1881年、中国浙江省紹興に生まれました。
比較的裕福な家庭に育ちますが、父が病に倒れ、伝統医学に頼っても治らず亡くなった経験から、封建的な制度や迷信への疑問を強く抱くようになります。
若い頃は日本へ留学し、はじめは医学を学んでいました。
しかし、「病気を治す前に、人々の精神そのものを変えなければならない」と考え、文学の道へ転向します。
1918年、短編小説『狂人日記』を発表し、中国初の白話(口語)小説として大きな反響を呼びました。
以後、『阿Q正伝』『故郷』などを発表し、民衆の無知や社会の矛盾、封建的な価値観を鋭く批判し続けます。
晩年まで、作家・評論家・翻訳者として活動し、1936年に上海で亡くなりました。
2.清(清王朝)の状況と魯迅の関係
清は、1644年に成立し、1912年に滅亡した中国最後の王朝です。魯迅が生まれ育った19世紀後半から20世紀初頭の清は、表面上は王朝として存続していながらも、内部も外部も深刻な問題を抱えた「衰退期」にありました。
もともと清は、満州族によって建てられた王朝で、長い間、漢民族を支配する立場にありました。そのため、政治の中枢には民族的な緊張があり、官僚制度や身分秩序は非常に硬直的でした。人々の社会的な立場は生まれによってほぼ決まり、努力だけで階層を超えることは容易ではありませんでした。
19世紀に入ると、欧米列強が軍事力と経済力を背景に中国へ進出します。アヘン戦争をはじめとする一連の戦争によって、清は敗北を重ね、不平等条約を結ばされました。港を開かされ、関税の権利を奪われ、外国の影響力が国内に広がっていきます。こうして中国は、形式上は独立国でありながら、実質的には列強に支配される半植民地状態に置かれるようになりました。
一方で国内では、人口増加と貧困の拡大、重い税負担、官僚の腐敗が深刻化していました。農民反乱や社会不安が頻発し、人々の生活は不安定さを増していきます。しかし、政治の中枢は旧来の制度を守ろうとする姿勢が強く、抜本的な改革はなかなか進みませんでした。
この時代の大きな特徴は、社会の現実は急速に変化しているのに、価値観や考え方は古いまま取り残されているという矛盾です。西洋の科学や思想が流入する一方で、迷信や封建的道徳、上下関係を重んじる意識が依然として強く残っていました。
魯迅が問題視したのは、まさにこの点でした。
貧しさや抑圧だけでなく、「それを当たり前として受け入れてしまう精神状態」こそが、社会を停滞させていると感じていたのです。
清末とは、王朝の終わりであると同時に、近代中国の始まりへ向かう過渡期。
希望と混乱、改革と絶望が入り混じった時代でした。
この背景を知ることで、魯迅の作品に込められた厳しい批判や、それでも捨てきれない希望の意味が、よりはっきりと見えてきます。
その他話し合ったこと
今回の作品、『故郷』は、「良かった」と感じる人と、「正直よく分からなかった」という人に、評価が真っ二つに割れました。
でも、こういう分かれ方をする作品ほど、物語そのものよりも、読者自身の人生観や価値観が強く反映されていることが多い気がします。
たとえば、「ルントウにはルントウなりの幸せがあるよね」と受け取るタイプの人。
社会の枠組みの中で生きてはいるけれど、その中なりに折り合いをつけて、自分の場所で生きている。
そう考えられる人は、どちらかというと我が道を行くタイプなのかもしれません。
他人と同じでなくてもいいし、自分なりの納得があればそれでいい、という感覚。
一方で、「このままでいいのか」「何かが間違っている気がする」と感じる人は、作中の「私」に共感しやすい傾向があります。
同じ違和感を抱き、同じ希望を持ち、一緒に考えられる仲間が欲しい。
そう思う人ほど、「ルントウの生き方をそのまま肯定していいのだろうか?」という問いが残るのかもしれません。
つまりこの作品は、「どちらが正しいか」を決める物語ではなく、自分はどちらの側の人間なのかを、静かに映し出す鏡のような作品なのだと思います。
良さが分からなかった、という感想も、深く刺さった、という感想も、どちらもその人自身の生き方がにじんでいる。
そう考えると、この評価の割れ方そのものが、すでに『故郷』という作品の面白さなのかもしれません。
まとめ
今回は魯迅『故郷』を、参加者の皆さんと意見を交わしながら読み進めました。多角的に読み解ける作品で、感想をシェアする中で新たな視点に気づかされることも多く、とても刺激的な時間となりました。
次回の読書会も、新しい物語と出会い、語り合えるひとときになることを楽しみにしています。初めての方も、どうぞお気軽にご参加ください!
次回作品と日程は決まり次第、こちらのブログにてお知らせします。
次回のご参加も心よりお待ちしております。



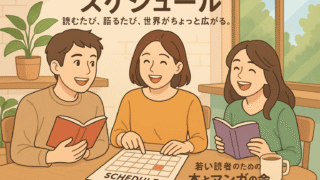


コメント